AI導入で「埋もれた求職者」を掘り起こす 日本教育クリエイトの挑戦
人手不足が深刻化するにつれ、人材サービス業の競争環境は厳しさを増している。日本教育クリエイトは、潜在的な求職者への効率的なアプローチに活路を見出し、AI自動架電システム「Mico Voice AI(ミコボイス AI) 」を導入。わずか半年間で求職者との接点を3倍に増やし、潜在層の掘り起こしに成功した。
過去の求職者データ活用が長年の課題に
日本教育クリエイトは1975年の設立以来、医療・福祉業界に特化した人材事業を展開、近年はIT業界にも進出している。独自の人材紹介・派遣サービスや生涯学習事業を通じて、求職者を多角的にサポートできることが強みだ。しかし、人材業界の競争が激化する中で、過去の求職者データを十分に活用しきれていないという課題があった。人的リソースの制約から、各支社で過去の登録者へ定期的にアプローチするのが困難で、この課題を解決するためにAI自動架電システムのMico Voice AIを導入した。
従来、求職者へのアプローチは電話が中心だった。しかし、1人の担当者が1日に100件、200件と電話をかけるのは現実的ではない。成果も出にくく、担当者のモチベーション維持も難しい。
実際、100人に電話をかけても求職者を1人見つけられるかというレベルだった。そのため、継続的な取り組みができていない支社がほとんどだった。メールでのアプローチも検討されたが、求職者の希望条件(フルタイム/ハーフタイム、居住エリアなど)が多岐にわたるため、本部で選別しそれぞれに適した求人情報を送付するのは難しく、全国規模での展開には向いていなかった。そのため、過去の求職者に対し、シンプルに「仕事を探しているか否か」という「現状確認」を効率的に行う新たな手段が求められていた。
このような背景から、同社は過去登録者データからの「掘り起こし」に着目。当初はLINE連携による求人情報送付なども検討したが、その過程でMico社との接点を持つ。Micoとのやり取りの中でAI自動架電の仕組みであるMico Voice AIの提案を受け、導入ハードルが低いことから有力な候補となった。
開発段階のMico Voice AIを選んだ理由
導入検討をしていた当時、Mico Voiceはまだ開発途上だった。その段階でも日本教育クリエイトがMico Voice AIを選んだのは、要望を迅速に製品に反映するMico社の姿勢を評価したからだった。
また、日本教育クリエイト 企画マーケティング部 部長の綿引敏丈氏は、新しい技術を活用する際の「ワクワク感」が導入を後押ししたとも語る。Micoが柔軟な対応をしてくれたことで、膨大な数の架電や細かなトーク設定など、試してみたいアイデアを次々に実現させられるだろうと判断できたのだ。
日本教育クリエイト 企画マーケティング部の廣瀬みちる氏は、Mico Voice AIの音声を聞いた際に「音声はAIだとは分かるが、思ったよりも会話に違和感がなく、これならボタンを押して回答するだけならやってくれそう」と感じた。Mico Voice AIは、日本語特有のイントネーションやスピード調整にこだわり、人間と遜色ない自然な会話を実現している。これにより、高い架電効果が期待できると判断したのだ。その上で、人的リソースでは限界のあった「数」のアプローチを可能にすることで、「掘り起こし」戦略を前進させられると考えられた。
2024年5月からAI自動架電の導入検討が始まり、6月には導入の方針が固まる。Micoとの間で具体的な料金や契約などを8月には確定させ、9月に設定を実施、10月からは早々に先行導入で運用を開始した。この時点でMico Voice AIは、まだ一般提供前だった。
導入当初、社内からは「本当に効果があるのか」「従来通りの電話対応で十分ではないか」といった懐疑的な意見も挙がった。これに対し企画マーケティング部は、各支社で過去の求職者へのアプローチにばらつきがある現状を指摘し、「Mico Voice AIの導入はプラスにしか働かない」と説明した。さらに、人による架電とAIによる架電コストの比較結果も示し、AIによる優位性も訴求した。
導入過程で最も重視したのは、支社の業務負担を極力減らす運用体制を敷くことだった。導入初期段階では、コールフローの設定やリストの調整など、Mico Voice AI運用に関わる全工程のうち9割は企画マーケティング部が主導で行った。これにより支社は、Mico Voice AIで掘り起こされた求職者への対応だけに集中できるようにした。また、「Micoチャットルーム」を設置し質問への対応体制も整え、月1回の振り返り期間を設けて成果を社内に周知しMico Voice AIの有効性の認識を促した。
架電数と接続率の最適化にも、導入初期にしっかりと取り組んだ。当初はコール数ごとの課金となる契約だったため、架電数が増えればコストがかさむ。そこで、1人当たりの架電回数を2回および3回でテストし、接続率を検証。双方に大差がないことが分かったため、コストを抑え多くの求職者にアプローチするために、架電回数を1人1回とする方針に転換した。
さらに、架電時間やトークスピードも調整した。トークスピードを速くすると、回答率が向上した。他にもトーク内容の変更など、約2週間単位でPDCAサイクルを回し、コールフローの改善を図った。たとえば、仕事を探していると回答した求職者がいれば、即座に担当者へ転送する仕組みに変更したところ、大きな成果が出ている。
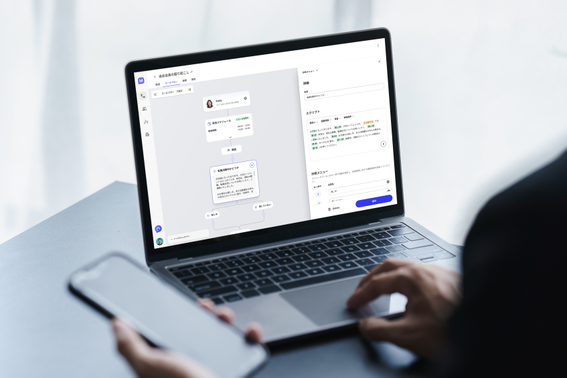
苦労したこともある。基幹システムへの履歴登録が手作業では困難だったため、新たにRPAを導入し自動化を図った。しかし、ロボットが停止することもあり、システム連携の重要性を痛感することになる。また、電話着信時に「迷惑電話の可能性あり」と表示され、一定数電話に出ない人がいるのも課題だった。これらには、運用しながら適宜対応している。まだまだ課題はあるものの、企画マーケティング部としては、会社全体の効率化と効果向上をミッションとして、継続して改善に取り組むこととなる。
接点3倍を実現した成果と、浮き彫りになった課題
Mico Voice AIの成果として、導入時から半年間で求職者との接点は3倍に増加、導入前のデータがないため実質的な効果はそれ以上だと綿引氏は推測する。この成果は、埋もれていた求職者層に効率的にリーチできるようになったことを示している。
導入当初は懐疑的だった社内の雰囲気も変わった。「想定よりも架電ができる」「有効な手段」といった声が上がり、Mico Voice AIは求職者確保の有効な手段として認識され始めている。また、AIが掘り起こした求職者へのアプローチ方法について各支社での議論が活発化し、組織全体で採用課題に取り組むきっかけにもなっている。
電話に未応答の求職者には、Mico Voice AIと連携したSMSフォロー施策が効果を発揮している。電話では接触できなかった層に対し、「お仕事紹介の日本教育クリエイトです」との簡潔な文面とアンケート回答用URLを送信し、不審電話ではなかったことを伝え、求職しているか否かの回答を促している。廣瀬氏によれば、「電話よりもSMSの回答率は良い」とのこと。SMSを送るきっかけはAIによる電話であり、それが求職へのアプローチの最適化につながっている。
また、Mico Voice AIは、人とは異なり疲弊せずストレスも感じずに架電できる。これにより、単純に「仕事を探しているか否か」を確認するだけでなく、特定の地域や具体的な求人案件に特化した架電など、より柔軟な運用が可能となっている。
一方で、接続率が向上しても、それがビジネスへの貢献に直接結び付くわけではない。接続率が向上するMico Voice AIの性能や機能よりも、架電後の運用にはまだ課題があると綿引氏。掘り起こした求職者へのフォローアップ体制を各支社でいかに整備するかが重要だ。今後は数を追うだけでなく、「質を高める運用」に注力していく。
AIと人が協業する未来へ
AIと人との役割分担について綿引氏は、求職者の掘り起こし、求職者確保、希望に沿った求人の検索といった「効率が求められる業務はAIが圧倒的に主流になる」と展望する。一方で、求職者の潜在的な希望のヒアリングや、応募後のきめ細やかなフォローアップなどは、「人だからこそ担える役割として残る」と考えている。AIと人との協業でより、質の高いサービスを提供する未来を描いている。
短期的な展開として、基幹システムとのAPI連携によるさらなる業務効率化がある。現在、RPAを用いて基幹システムへの履歴登録を行っているが、RPA停止時のエラー対応など運用上の手間が発生している。今後、Mico Voice AIと基幹システムを連携させることで、履歴登録の手間がゼロになり、業務負荷が大きく軽減されることを期待している。また、手作業で行っている架電リストの抽出作業も、システム連携により条件選択だけで自動予約できるようにしたいとも考えている。
他にも求職者とのコミュニケーションでは、LINE、AIコール、SMSといった複数チャネルを組み合わせて、ターゲット層の年齢の違いなどを考慮し最適なチャネルを使い分けることが重要となる。全てのチャネルを同時並行で活用し、求職者との接点を多角的に持つことで、より多くの機会を創出していくことを考えている。