モノがつくれて、コトが起こせれば起業もできる、そんな人材を育む神山まるごと高専の学びの形
神山まるごと高等専門学校は、徳島県神山町に2023年4月に開校した私立の高等専門学校だ。高等専門学校は全国に58校あり、国立が51、公立が3校、私立は4校しかない。神山まるごと高専は、私立として実に19年振りに新設された高専だ。
同校は、多くの企業や個人がさまざまな形で支援している。開校当初から資金提供を行っているファウンディングパートナー、学費の実質無償化を実現するために、奨学金への拠出・寄付を行っているスカラーシップパートナー、共に授業をつくり、学生たちに学びを提供するプログラムパートナーがある。スマートロックのソリューションを展開するフォトシンスは、リソースサポーターとして支援している。
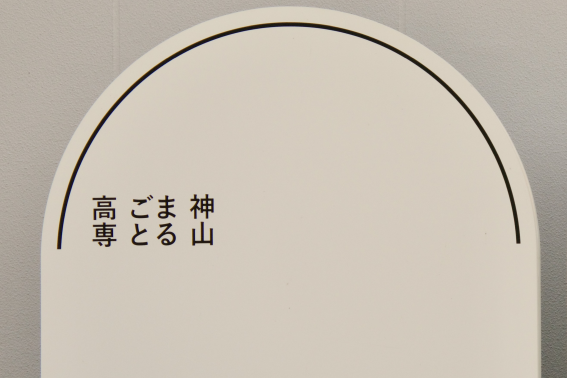
5年間一貫して学べる高専のメリット
神山町は、人口約5000人の小さな町。同町で2000年代初頭から始まった、地域活性化の取り組み「神山プロジェクト」は、「創造的過疎」という言葉を掲げ、IT企業のサテライトオフィス誘致や移住促進など、都市部の人材や資源を積極的に取り込みながら独自の地域づくりを進めている。
神山まるごと高専は、そうした神山町の地域づくりの流れを汲み、町全体を学びの場と捉え、「テクノロジー×デザインで人間の未来を変える」との理念の基に設立された。同校の特長は、神山町全体を学びの場とし、地域住民や企業との連携を重視した教育を展開していることだ。
神山まるごと高専は「デザイン」「テクノロジー」「起業家精神」の三つを柱に、社会で必要とされる実践的なスキルを習得できるカリキュラムとなっている。1学年40名程の少人数制で、学生一人ひとりにきめ細やかな指導を行う。学生は全員が寮で生活し、共同生活を通じ協調性やコミュニケーション能力を育む。さらに、大学教授や企業の第一線で活躍する専門家など、多様なバックグラウンドの教員が指導にあたるのも他にはないものだ。
校名の「まるごと」には、テクノロジーとデザインをかけ合わせることを学び、起業家精神、さらには課外活動や寮生活など、全てをまるごと含めデザインし考えるキャンパス、との意味が込められている。
中学校を卒業した後の5年間を一貫して学ぶ高専には、さまざまなメリットがある。一つが、大学受験がないことだ。大卒の人たちに高校で何を学んだかを訊ねれば、「大抵の人は受験勉強を思い浮かべるはずです」と言うのは、神山まるごと高等専門学校 事務局長の松坂孝紀氏だ。高校で苦労して受験を乗り越え、ようやく大学に入った1年目はモラトリアムを満喫、3年になれば就職活動が始まり、4年は卒業論文に追われる。

高専は高校、大学の7年を、5年に凝縮して学ぶ。その分の忙しさはあるが、学ぶ意志を持った学生が、集中した5年間を過ごせる。15歳から専門分野に特化した教育を受けるため、深い専門知識と高い技術力を早い段階で習得し、実験や実習、課題解決型の学習を通じ、座学で得た知識を活かす実践力を磨く。それらで、課題に対し自ら考え、解決策を見出す能力を養う。
テクノロジーとデザインをかけ合わせ魅力的なモノを生み出せる人材
神山まるごと高専の設立構想が生まれたのは、2018年だ。設立発起人は、Sansan株式会社 代表取締役社長の寺田親弘氏。Sansanは2010年に、神山町にサテライトオフィス「Sansan神山ラボ」を開設している。これは、築100年の古民家を改修した趣のあるオフィスで、社員が常駐勤務しており、集中議論や研修などにも活用されている。
サテライトオフィスの開設をきっかけに、Sansanと神山町の関係は深まった。社員が神山町に移住して地域イベントに参加し、神山町の特産品も社内で販売する。さまざまな交流が行われる中、寺田氏は神山町の地域活性化の取り組みに感銘を受け、神山まるごと高専の設立を構想する。
2019年に「神山まるごと高専設立準備委員会」が発足、具体的な設立準備が始まる。委員会には、寺田氏をはじめ、教育者、IT企業の経営者、地域住民など多様な分野の人が参加、教育理念やカリキュラム、学校運営などについて議論を重ねた。2021年10月に、文部科学大臣に設立認可申請を行い、2022年8月に認可、2023年4月に開校した。同校の設立者は「学校法人神山学園」で、理事長に寺田氏が就任した。
テクノロジーとデザインをかけ合わせ、魅力的なモノを生み出す。それを社会に貢献させるための起業家精神を、神山まるごと高専では学び養う。これを象徴する授業が、入学し最初に行う「ITブートキャンプ」だ。これは4日から5日にわたり集中して実施する授業で、内容は神山町の地域課題を、テクノロジーを用いて解決する。
松坂氏は、「中学校を卒業したばかりの学生たちですが、これから生活する神山町の地域課題は何で、それをどのように解決するかを考えアイデアを出し、プロトタイプを作り発表します」と説明する。技術力はまだあまりないが、今後の5年間で何を学び、どのように地域社会と関わっていくかを、真っ先に実践し実感する。
さまざまな形で学校運営、学生の学びを支援するパートナーの存在
私立高専は、国立に比べ学費が高くなるのがデメリットだ。これに対し神山まるごと高専では、スカラーシップパートナーなどから集めた寄付金を活用し、奨学金制度などを用い学費の実質的な無料化を目指している。具体的には寄付金などで集めたお金で奨学金基金を設け、資産運用し安定的な奨学給付を実現している。スカラーシップパートナーには、デロイトトーマツ、ソニーグループ、ソフトバンク、富士通、Sansanなど蒼々たる企業が名を連ねている。

金銭面の支援だけでなく、学ぶ面でも多くの企業や個人が支援している。神山まるごと高専の教育における三つの柱の一つに起業家精神がある。同校で学び、社会に役立つ人を育てたい。社会に役立つには、卒業後に即戦力人材として企業に就職し働くキャリアパスがある。加えて、起業もパスの一つとして想定している。「モノがつくれて、コトが起こせるならば、シンプルに起業ができるのでは、そういう発想を持っています」と松坂氏は言う。
多くの中学生、高校生にとって、起業は特別なものだろう。神山まるごと高専の学生には、起業がキャリアパスの選択肢となるよう、日頃から起業家と学生の接点を持つようにしている。たとえば、毎週水曜日には「起業家講師Night」を開催し、起業家を招いた課外授業を実施、各起業家講師が自身の生き方や価値観を熱くプレゼンする。学生たちは、さまざまな経験を積んでいる講師と悩みややりたいことを近い距離で直接相談できる場となっている。
神山まるごと高専では、自身のキャリアとして起業を選択肢に考える学生が、一期生の入学時に約70%もあった。2年生になるとそれが80%に上昇している。もともと起業への意識が高い学生が集まる上に、1年間の授業、起業家とのコミュニケーションを通じ、キャリアパスで起業を強く意識するようになるのだ。
一般に高専生1人に、20社以上の求人があると言われる。引く手あまたの状況の中、80%が将来の選択肢に起業を入れている。実際は、大学への編入や企業への就職の道を選ぶ学生も少なくないだろう。多くの学生が大学受験を乗り越え就職に有利な大学に入り、大学では就職活動に苦労し大手企業への就職を目指す。そのような学生生活を否定はしないが、神山まるごと高専での濃い5年間を過ごし起業が当たり前になっている学生のほうが、今後の社会の変革に大きく貢献しそうだ。
実際、一期生は1年次から他の高校生や大学生ではできないような経験をしている。その一つに、世界最大級のロボット大会である国際ロボットコンテストへの参加がある。一期生の学生たちが、自らこの大会に出たいと要望した。ハワイで地区予選が開催されるため、参加には大きなコストがかかる。渡航費や参加するためのロボット製作など、最低でも300万円は必要と考えられた。
学生たちは、お金を集めるところから取り組んだ。結果的に、目標を上回る750万円の支援を取り付けた。今回、予選は残念ながら通過できなかったが、ルーキー賞を獲得した。この経験を経て参加した学生たちは、次は1000万円を集めてまた挑戦したいと言う。学生が自主的に考え行動し、このような大きな挑戦をする。それを学校、パートナー企業も支援する。「ここに教育の本質が詰まっていると思います」と松坂氏は言う。
リソースサポーターとして電子鍵で支援するフォトシンス
神山まるごと高専を支援するパートナーには、さまざまな形がある。その一つが、物品提供、サービス提供を通じ、開校、学校運営を支えるリソースサポーターだ。
神山まるごと高専の学生寮や食堂がある建物「HOME」は、旧神山中学校の校舎をリノベーションし利用している。リノベーションには、地元の神山杉が数多く利用されている。授業を行う校舎となる「OFFICE」も、神山杉を使い新設された。

これら学校施設の出入り口管理に利用されているのが、リソースサポーターのフォトシンスが提供する電子鍵ソリューション「Akerun入退室管理システム」だ。校舎や寮の建物は高い塀に囲まれておらず、オープンな形で運用されている。学校の安全管理のために、建物への出入り口などは適宜施錠されている。学生や教職員は、電子鍵となっている学生証や職員証を使い、扉の鍵を解錠し出入りする。

5階建てのHOMEの建物は、3階以上は学生が生活する寮となっている。この建物の出入り口には、Akerunの電子錠が設置されている。さらに、学生の生活スペースとなる3階の入り口にも電子鍵がある。また男子、女子のゾーンの境界にもAkerunがあり、それぞれへの出入りが制御される。このようにエリア毎に、適切な人だけが解錠し出入りができるよう、Akerunを使いきめ細かな制御がなされている。
たとえば、教職員が利用する会議のスペースは、日常的には学生も自由に出入りができる。しかし、情報の管理が必要な教職員会議などが実施される曜日の該当時間帯だけは、学生がそのエリアに入れないよう制御されている。
Akerunで個々の出入り口単位で、きめ細かい開閉権限の制御ができるのは、学校運営の安全性確保と鍵管理の効率性を大きく向上している。これが出入り口毎に複数の物理鍵で管理するとなれば、学校という大きな建物では大量の鍵を管理しなければならない。たとえば、学生が授業の必要から入りたい部屋があれば、教職員室に鍵を借りに来て、都度該当する鍵を貸し出す。貸し出し状況を紙の台帳などで管理するとなれば、相当な手間がかかるだろう。
Akerunなら、複数の鍵をクラウド上で一元的に管理できる。全員に電子鍵を配り、職員か学生か、性別などに応じ、カテゴリー化し権限を付与できる。特定のエリア、特定の時間だけ施錠するような制限も容易に実現できる。
もう一つのAkerunのメリットが、大がかりな工事を必要とせず、後付けで電子鍵を設置できることだ。建物をリノベーションし再利用しているため、コスト面からも既存設備は最大限に利用したい。既存の扉にも簡単に電子鍵を追加できるAkerunは、リノベーションの建物の出入り口をインテリジェント化するには最適な選択肢と言える。
既に学生たちは、入学時からこの電子鍵を用いた生活に慣れている。日常生活の中に、電子鍵が違和感なく浸透しており、アクセス可能なところは学生証を使い解錠し、解錠できないところには入れないのが当たり前となっている。
2024年10月26日、27日に開催された神山まるごと高専の文化祭「まるごと祭 2024」では、学生が日常的に利用しているAkerunを、文化祭を見に来た顧客に紹介する展示も行われた。身近で利用しているAkerunのようなIoT技術を活用する新しいアイデアが、学生から出て神山町の生活の中の課題解決も期待される。
学生の自主性を尊重し、専任の教職員だけでなく、さまざまなパートナーが支援する神山まるごと高専。その上で学費の無償化にも取り組んでいる同校は、かなり理想的な学びの場と思われる。サポートするパートナー企業には、優秀な人材を獲得したい思惑も多少はあるかもしれない。しかし、彼らの取り組みは、これからの日本の社会変革を支える人材を育むことにあると考えられる。だからこそ、パートナー企業のトップ自らが多数、時間を割いて学生たちと語り合うために神山町を訪れている。こういった新しい学びの場が、今後は神山町以外にも展開されることに期待したい。
This is an article about Kamiyama Marugoto College, a new private higher education institution in Kamiyama, Japan. It discusses the school's curriculum, which is focused on technology, design, and entrepreneurship, and its unique approach to education, which emphasizes community involvement and real-world experience. The article also details the school's efforts to make education more affordable, as well as the support it receives from various partners. Some important points are that the students live in dorms, and the school has a scholarship program. Also, the students get to work on solving real-world problems, like participating in the International Robot Contest.