ニコンがAIで需要予測改革 研究開発部門主導の自動化にDatabricks活用
大手光学機器メーカーのニコンは、カメラアクセサリ約3000SKUの需要予測向けに、Databricksを活用したAIシステムを構築した。これにより、従来は月30時間以上かかっていた業務を3〜4時間に短縮し、対象製品の需要予測を99%自動化することに成功した 。複雑な需要パターンを持つ少量多品種製品の予測精度をいかにして向上させたのか。その道のりを追う。
カメラアクセサリの多様なニーズが需要予測を複雑に
カメラアクセサリは時期を問わず数多く購入されるものもあれば、購入が希なものもある。また、カメラやレンズといった主要製品と比較し、極めて多様なカテゴリーにわたっており、それぞれの製品で需要パターンが大きく異なる。さらに、多くのアクセサリはサプライヤーからのリードタイムが極めて長く、在庫管理が難しい。
特に、販売量が少なくても顧客に不可欠な製品が多いことが、需要予測を困難にしていた。月の平均販売数が5個未満のSKUが大半で、1年の半分以上、売り上げがない製品も珍しくない。しかし、顧客が必要とする際に確実に供給するために、在庫は確保する必要があった。また、一部のアクセサリの需要はカメラ本体と密接に関連している一方、ほとんど関連性のない製品も存在する。こうした多様なニーズが、予測難易度の高さにつながっている。
加えて、ニコンはグローバルで販売子会社10社の販売計画を統合し、約3000のSKUを管理する必要があった。コロナウイルス感染症の影響でリードタイムが長期化し、18ヶ月から24ヶ月先までの販売計画が求められていた。これらの計画は、10の海外販売子会社の担当者が手作業で集計・作成し、毎月30時間以上を費やしていた。そのため詳細なチェックの時間が不足し、計画の精度が低くなり、結果として過剰在庫、在庫不足の要因となっていた。
これらの課題に対し、当初はAutoMLや従来の機械学習手法を使った需要予測を試みたものの、アクセサリの多様性、特にローボリュームアイテムの需要パターンを適切に処理できず、期待する精度が得られなかった。一部のアクセサリはカメラの販売に連動しているものの、全てがそうではないという複雑性も、単一の手法では対応が困難であることを浮き彫りにした。
この試行でSKUの76%は需要予測を自動化でき、作業時間を月30時間超から3〜4時間へ削減。人間と同等レベルの予測精度も実現した。しかし、残る24%の極端に販売量が少ない製品(スーパーローボリューム品)の需要予測は手作業が必要だった。この「不完全な自動化」が、システム活用の最大の障壁となった 。計画担当者からすれば、一部を手作業で行うのであれば、全体を自分で確認したいとの心理が働き、システムの全面的な導入は進まなかった。
研究開発部門がモデル開発からデプロイ、継続的な監視までカバー
そこで、需要予測のさらに踏み込んだ課題解決に向けてニコンが活用を本格化したのがDatabricksだった。背景には、「単なるツール選択以上の戦略的な意図がありました」とニコン 先進技術開発本部 数理技術研究所 第三研究課長 博士(工学) の西野峰之氏は言う。

ニコンは、2019年頃から社内のデータ活用基盤としてDatabricksの利用を開始していた。ニコン社内のデータ活用では、SQLを中心とするデータベース管理と、Pythonを用いたアルゴリズム開発(機械学習など)の両方のニーズがあった。Databricksは、SQLとPythonの双方を同じ環境で扱える特性から、社内の研究開発部門におけるデータ活用推進の主要なツールとなっていた。
当初、Databricksは主に研究開発(R&D)フェーズでのプロトタイプ開発に利用されていた。しかし、プロジェクトが進むにつれ、R&D部門が開発したモデルが実際の業務システムに統合され、運用されるまでのプロセス全体を自分たちで完結できる可能性が見えてきた。
R&D部門が開発したモデルの実用化には、従来、システム統合が必要で、情報システム部門を通じた外注などに多大な時間と費用を要していた。また、統合後は開発者がモデルの性能監視などに関与しにくい課題もあった。
Databricksが提供するMLOps(機械学習モデルを効率的に開発・運用する手法)の概念や、Unity Catalog(データとAI資産を一元管理するガバナンス機能)、MLflow(機械学習のライフサイクルを管理するツール)といった機能群は、開発からデプロイ、継続的な監視までの一連のプロセスをシームレスに自動化できる 。これにより、システム統合期間を大幅に短縮し、実運用後も開発者が性能を継続的に監視・更新できる体制を構築できると判断した。これは、研究開発部門が単にモデル開発や概念実証(PoC)を実施するだけでなく、実際のビジネスに与える影響までをコントロールできるという大きな変革を意味する。
ハイブリッド型需要予測システムで99%自動化
ニコンは、アクセサリ製品の複雑な需要パターンに対応するため、Databricks上で新たな需要予測システムを構築した。まず、初期の試行から得られた教訓として、異なるSKUには異なるモデルが必要との結論に至った。そこで、Databricks上で、複数の統計モデルと機械学習モデルの予測精度を動的に評価するシステムを構築した。
このシステムでは、アクセサリとカメラ、両方の過去の販売データを使用し、各SKUに対し最適なパフォーマンスを発揮するモデルを自動選択し、予測を生成する。これにより、各SKU固有の需要パターンに合わせ最適なモデルを適用し、全体的な予測精度を向上させる。
ニコン 先進技術開発本部 数理技術研究所の欧陽和雅氏は、従来手法では高精度の需要予測が困難だったスーパーローボリューム品に「思い切ったシンプルな戦略を採用しました」と語る。複雑なアルゴリズムではなく、過去6ヶ月の合計販売数を、将来6ヶ月の予測需要合計値とする手法だ。たとえば、18ヶ月分の計画であればこれを3倍する形となる。計画担当者のフィードバックに基づき、直近2ヶ月の計画は前月の計画と同じ値に固定し、残りの期間に需要を均等に配分するという調整も加えた。
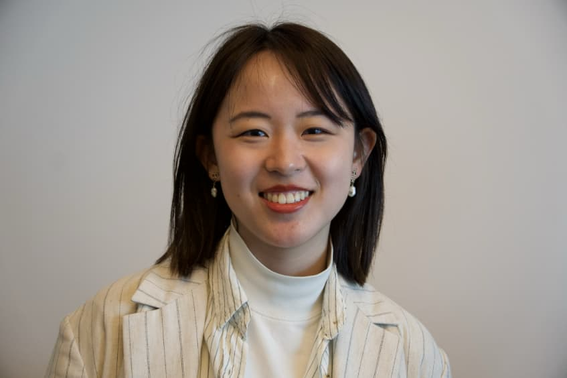
このアプローチは極めてシンプルであるにもかかわらず、人間による予測と同程度の精度を達成し、予測計算にほとんど追加の時間を要さなかった。何より、この手法でスーパーローボリューム品を含む全アクセサリの99%は需要予測関連業務を自動化できた。急激な需要増加や特需などの際には、担当者が販売計画を修正する必要があるが、「計画担当者の手作業による負担は大幅に軽減されました」と欧陽氏は説明する。
需要予測フレームワーク全体は、Databricks環境内で構築され、一連のDatabricks Notebooksを通じて実行される。複数ソースからのデータ取り込み、前処理、モデル選択、予測、出力までが単一のワークフローで完結する。データの整理には、Delta Lake(信頼性の高いデータレイクを構築するためのストレージ技術)上で、未加工データ(Bronze)、検証・クレンジング済みデータ(Silver)、集計済みビジネス用データ(Gold)という3層のテーブル構造が採用されており、データ変換の来歴(リネージ)が容易に確認できるようになっている。生成された予測結果は、ニコンの既存の計画・発注システムとPower BIダッシュボードに直接フィードされる。
MLflowは、プロジェクトの成功に不可欠な役割を果たしている。開発段階では、MLflowが過去の販売データ、モデル設定、トレーニング結果、各SKUにおける各モデルのパフォーマンスなど、あらゆる情報を追跡記録する。これにより、異なるモデル間の比較が容易となり、どのモデルが良好に機能しているか、機能していないかを迅速に特定できる。また、プロダクション移行後も、MLflowは実際の販売データが入力されるにつれ予測精度を継続的に監視し、モデルのパフォーマンス低下や注意が必要な状況を検知できる。MLflowの活用は、「モデルの透明性と柔軟性を高め、予測精度の向上と変化への迅速な対応を可能にしています」と欧陽氏は評価する。
現在、予測フレームワーク全体は、Unity Catalog、Spark、Delta Lake、MLflow、Databricks WorkflowsといったDatabricksの機能をフル活用し構築されている。システムは実装準備を終え、テストを経て2025年8月の本格運用を予定している。
意思決定から実行までのリードタイムを大幅に短縮
ニコンにおけるDatabricks導入は、単なるツール導入に留まらず、組織文化と業務プロセスの両面で効果をもたらしている。まず、計画担当者の作業効率は大きく向上した。カメラアクセサリの99%で需要予測が自動化されたことで、通常時は計画担当者が手動で予測を行う必要がなくなり、より戦略的な業務に集中できるようになった 。予測精度も人間によるものと同等以上で、大きな予測ミスが減少するなど顕著な効果が表れており、在庫の最適化につながっている。
需要予測モデルを開発する研究開発部門の役割も進化した。Databricksの活用により、データ準備から本番デプロイまでを一貫して内製で行える環境を整えたことで、開発から運用までの自動化を実現し、従来は外部委託していたシステム統合の時間とコストを削減した。意思決定から実行までのリードタイムは大幅に短縮できたという。
また、Databricksはチーム内のコラボレーションも向上させている。以前は各開発者が個人のローカル環境で作業していたため、互いの進捗が見えにくく、重複作業や知識の共有不足といった課題があった。しかし、Databricksの共有ワークスペース上では、チームメンバー全員が互いのコードや作業状況をリアルタイムで確認できる。そのため、共同作業が容易になり、担当者が突然休んだ場合でもプロジェクトの進行に支障が出にくくなった。
総じて、ニコンはDatabricksを「単一のプラットフォームで、データ入力から計算、開発から実運用の環境まで全てをスムーズに行える」ツールとして高く評価している。
エンドツーエンドの完全自動化サプライチェーン最適化システムを目指す
ニコンのDatabricksを活用した需要予測プロジェクトは一旦、成果を上げたが、今後の進化に向け課題も認識されている。まず、極めて販売が不規則なスパースな需要の予測は依然として困難だ。これは機械学習や統計手法の限界に挑戦する領域であり、需要予測以外の運用的なアプローチも視野に入れ解決策を模索している。
次に、MLflowのオートロギング機能は極めて有用な一方で、システム全体のパフォーマンスを若干低下させる可能性がある。今後は、Spark APIや分散計算、UDF(ユーザー定義関数)などの最適化手法を導入し、MLflowの効率性を向上させることも検討している。
また、予測結果の説明可能性(Explainable AI)の欠如も課題の一つだ。予測結果をステークホルダーに納得感を持って説明するには、説明可能性の 機能強化が不可欠となる。
今後の計画としては、外部データのさらなる統合を進め、予測モデルの堅牢性を高めることを目指している。現時点では月に一度の予測頻度であるため、デプロイ後やプロダクション段階でのパラメータチューニングが可能だが、将来的に週次など予測頻度を上げる場合は、開発段階でのチューニングを強化し、最適な設定をスムーズに本番環境に移行できるようにする意向だ。欧陽氏は「継続的開発の仕組みを、MLflowを活用して構築していくことを計画しています」と話す。
最終目標は、需要予測、在庫管理、販売計画から生産計画までを連携させ、エンドツーエンドで完全に自動化されたサプライチェーン最適化システムを構築することだ。西野氏は「Databricks上にさまざまなデータが集約されれば、それらを相互に連携させることで、サプライチェーン全体の最適化をよりスマートかつ効率的に実現できると見込んでいます」と展望を語る。
#Nikon #Databricks #AI #MachineLearning #DemandForecasting #MLOps #MLflow