北陸コカ・コーラ、OCI活用で災害リスクを乗り越えデータドリブン経営へ
清涼飲料水の製造・販売を主軸とする北陸コカ・コーラボトリング(以下、北陸コカ・コーラ)は、富山・石川・福井・長野の4県で地域に密着した事業を展開している。創業60年以上の歴史を持ち、長年蓄積してきた膨大なデータの活用を、成長のための重要施策と位置付ける。その基盤として新たに導入したのが、「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」だ。データドリブンな経営基盤の構築と、AI時代に向けた「エリアマーケティング3.0」構想の実現を目指す北陸コカ・コーラは、なぜOCIを選択し、今後に何を見据えているのか。
創業以来の財産「データ」を生かすための25年にわたる挑戦
富山県高岡市に本社を置く北陸コカ・コーラは、1962年6月5日に設立された歴史ある企業。コカ・コーラ指定会社として、北海道コカ・コーラボトリング、みちのくコカ・コーラボトリング、コカ・コーラボトラーズジャパン、沖縄コカ・コーラボトリングの各ボトリング会社とともに、全国に5社あるコカ・コーラボトラーの一翼を担っている。年間の販売実績は約21億本という規模だ。
同社の事業エリアは北陸三県と長野県という限定された地域だが、事業特性上、それでも膨大なデータが生み出されている。自動販売機や店舗など約5万5000箇所の販売拠点で、日々約400品目の商品が流通している。さらに、スーパー、自動販売機、ドラッグストアといったチャネルごとに商品価格が異なるため、同じ製品でもデータ上は異なる商品として扱われる。結果として莫大なデータ量となるのだ。執行役員 社長補佐 コーポレートプランニング統括部 統括部長の藤本一志氏は、「マーケットは小さいものの売り場がたくさんあり、そこから生まれるデータはものすごい量です。これが当社の最大の財産です」と語る。

膨大なデータの活用は、同社にとって長年の重要なテーマだ。現会長の稲垣氏が約25年前に提唱した「エリアマーケティング」戦略は、その先駆けだ。当時から顧客や売り場のデータベース化を推進し、飲料が飲まれる機会や場所を細かく分析、データとして蓄積する取り組みを進めてきた。
同社のエリアマーケティングは、時代の変遷とともに進化してきた。エリアマーケティング1.0の時代は、現場担当者が顧客データや店舗情報を手作業で調査・入力しており、データ生成に膨大な人手がかかり、効率が上がらないという課題があった。続くエリアマーケティング2.0時代は、エリア特化の担当者を配置したものの、データ作成専門の要員が100人規模で必要になるなど、「人手に頼る部分が多くなり、運用が滞りがちになりました」藤本氏は振り返る。
これら一連のマーケティング活動と並行して、同社ではオンプレミス環境で長い時間をかけてデータの集約と一元化を図ってきた。基幹システムのデータベースにはOracle Exadataを採用し、VMwareベースの仮想化基盤でさまざまなアプリケーションを構築・運用してきた。
クラウド移行を後押ししたのは複合的な要因
北陸コカ・コーラは近年、ITインフラのクラウド移行を検討してきた。その背景には、複数の課題があった。第一に、ハードウェアの老朽化と運用負荷の増大が挙げられる。オンプレミス環境のハードウェアが更新時期を迎え、ストレージの常時監視などで従業員が夜間対応をせざるを得ない状況も生まれていた。一方で、会社全体ではスーパーフレックスや在宅勤務といった働き方改革が進められており、ITインフラの運用体制の変革は急務だった。
第二の課題はレガシーシステムのブラックボックス化だ。長年の積み重ねで作り上げられた多様な個別システムやアプリケーションは一部がレガシーシステム化し、構築時の担当者が不在となったものもあった。「中身は分からないが、なんとか動いている」状況だったという。解決策として同社は、SaaSやPaaSを活用し、汎用的な業務アプリケーションは極力標準化する一方で、独自のエリアマーケティングデータや分析軸などは個別に作り込む方針を定めた。
電源装置の更改時期も迫っていた。2025年には更新が必要となり、サーバーOSのサポート切れにも対応する必要があった。仮想化基盤の一部をクラウドへ移行することで、これらの更改に伴う作業や費用を削減したいと考えた。
さらに、AI時代への対応も重要な動機だった。同社はAIの開発を進めており、将来的なAI活用を見据えたデータ基盤の構築が必須だった。
このような要件がクラウドへのシフトを導いたと言えそうだが、クラウドはIT部門が新たな役割を果たすためのプラットフォームとしても重要だった。北陸コカ・コーラは2023年にシステム開発子会社だったヒスコム社を吸収合併。これによりIT部門の意識は、より本質的なビジネスの成長に貢献すべきという方向にシフトしたという。コーポレートプランニング統括部 ITマネジメント部 システム企画課の上田繁氏は「オンプレミスは自由が利きますが、ビジネスのための柔軟性と迅速性といったメリットを得るにはクラウドを活用すべきだと判断しました」と話す。
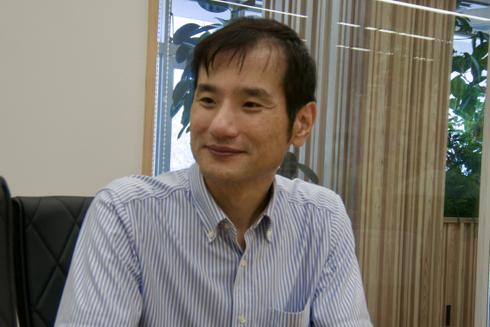
さらに、「2024年1月1日に発生した能登半島地震は、当社のクラウド移行の意思決定を後押ししました」とコーポレートプランニング統括部 ITマネジメント部 システム企画課の釣 大輔氏は続ける。BCP(事業継続計画)対策とデータ資産の重要性を再認識する契機になったのだ。既存の災害対策環境では、本社の建物内に予備機を設置していたため、大規模災害時には両方が影響を受ける可能性があった。クラウドで複数リージョンを活用すれば、BCP対策を強化できると考えたという。

性能、コスト、BCP......多角的な比較検討の末の「最適解」
北陸コカ・コーラは最終的にクラウドサービスとしてOCIを選択したわけだが、その大きな理由の一つが、既存のExadataとの互換性と性能の高さだ。同社の基幹システムは長年Exadataで運用されている。OCIの「Oracle Exadata Cloud Service」は、オンプレミス環境と同等の互換性とパフォーマンスを提供し、スマートスキャンといったExadata特有の高速処理機能をクラウド上でも利用できる。
OCI上でVMware環境を提供する「Oracle Cloud VMware Solution」(OCVS)の存在も、OCIの採用を後押しした。前述のとおり、同社はオンプレミスでVMware環境を広範に利用していた。上田氏は、「OCVSによって既存のVMware環境を迅速にリフト&シフトでクラウドへ移行できる点を評価しました」と話す。藤本氏も、「移行のスピード感は重要でした」と振り返る。将来的にはVMwareからの脱却を視野に入れつつも「最初のステップとして大規模なアプリケーション改修を伴わずにクラウド移行を進めるという観点で、OCVSは最適な選択肢でした」と話す。また、OCVSはアプリケーション基盤とExadataが分かれてしまうことによるネットワーク遅延を回避するのにも有効だったとしている。
BCPの観点でも、東京と大阪の2リージョンでOracle Exadata Cloud Serviceを導入することでデータを確実に守り、より強固なBCP対策を実現できると評価した。
コスト面のメリットもある。オンプレミス環境では、ハードウェアの導入費用や維持管理費に加え、24時間365日の監視体制にかかる人件費など、見えにくいコストが膨らんでいた。OCIへの移行のコスト試算は、短期的な運用コストはオンプレミスと大差がないものの、長期的には人件費を含む全体コストの削減が見込まれるという結果になった。特に、「24時間365日の自社運用が不要になる点は非常に大きいです」と藤本氏は語る。また、事業の状況に応じリソースを柔軟に増減でき「臨機応変に運用できる」クラウドの特性は大きなメリットだという。
さらに、OracleはNVIDIAとの協業を深めるなど、AI分野への注力姿勢を強めている。このことは、北陸コカ・コーラにとって大きな期待感につながった。将来的にはExadataからのデータパイプラインにより、AIを含めたデータ活用の効率化にも期待しているとしている。
もちろんOCIの選定に際しては、他の主要なクラウドベンダーとも詳細な比較検討を行った。データベース性能と互換性、運用性、災害対策、費用といった多角的な観点から比較し、北陸コカ・コーラの既存のExadata資産を最大限に活かしつつ、上記の課題を解決できる最適な選択肢として、OCIを評価した形だ。
クラウド移行は序章、AI活用で「エリアマーケティング3.0」の実現へ
OCIへの移行は、現在進行中だ。クラウド基盤の構築は完了し、サーバー移行を順次進めている。2026年2月までには、Exadataのクラウド化を完了させる予定だ。
北陸コカ・コーラは、OCI導入を足がかりに、さらなるデータ活用とビジネス変革を目指している。同社は、新たな「エリアマーケティング3.0」構想の実現のために、「あるべきところに売り場があり、あるべき製品があり、そこに消費者がいる」という理想的な状況を作り上げることを目標としている。具体的には、飲用機会を正確に捉え、最も効果的な販促活動や品揃えを行う。そのために、AIを活用したシミュレーションも導入する。棚割りや最適な計画を立案・実行するためのS&OPシミュレーター、販促・価格シミュレーター、充填ルート最適計算、ロケーションシミュレーターなど具体的なAI活用も構想している。
また、単なる予測に留まらず、店頭やオペレーションの変革を目指し、自社データだけでなく、マーケットデータやエリア情報も取り込み、継続的に更新していく。UI/UXも重視し、全社員が直感的・簡便に利用できる仕組みを目指す。
クラウド化やAI導入は、人の仕事を奪うのではなく、人とシステムがそれぞれの得意分野を生かして協働する体制を構築するのが目的だ。北陸コカ・コーラは、人による調査や入力といった定型的な作業はシステムに任せ、従業員は分析や企画といった、より創造性が求められる高度な業務に集中できるようにしたい意向だ。藤本氏は人事も兼務しており、人とシステムの最適な分担を常に検討していくという。
北陸コカ・コーラにとって、OCIの導入は単なるシステム移行ではなく、データドリブンな経営への転換、そしてAI時代における新たなビジネスモデル構築に向けた戦略的な一歩だ。オンプレミス環境における長年の課題を解決しつつ、能登半島地震で再認識されたBCPの重要性にも対応する。より強固で柔軟なIT基盤を手に入れ、変化の激しいビジネス環境において持続的な成長を目指していくことになる。