イトーキが、Oracle AIで自動倉庫の予知保全システムを開発
イトーキは、物流業界の人手不足と需要拡大に対応するため、OracleのAI・データ基盤を活用し、シャトル式自動倉庫「システマストリーマー SAS-R」向けの予知保全システム「スマートメンテナンス」を開発した。11月5日に、イトーキおよび日本オラクルが発表した。
このシステムは「リモートメンテナンス」と一体化させた保守サービス「ITOKIアドバンスドメンテナンス」として、2026年1月に提供を開始する。イトーキ 代表取締役社長の湊 宏氏は、本取り組みを「物流現場の生産性と安定稼働の両立をリードする新たな挑戦」と位置づけ、同社の設備機器・パブリック事業をワークプレイス事業に次ぐ第二の柱にする意向を示している。

保守ビジネスの転換とIT/AI戦略
イトーキは、オフィス家具の製造と販売を行う「オフィス1.0」、オフィス設計や空間づくり、働き方のコンサルティングを行うことで価値を高める「オフィス2.0」を経て、現在はITやIoT、AIを活用したオフィス環境の生産性向上を目指す「オフィス3.0」をビジネスの中心に据えている。今回の開発は、オフィス3.0の戦略を物流倉庫領域に展開した一例だ。
オフィス3.0に注力し始めた同社における設備機器・パブリック事業は、連結売上高の約4分の1を占める。イトーキ 常務執行役員 設備機器事業本部 本部長の中村元紀氏は、「現在の約10%の保守売上比率を、将来的に30%まで引き上げることを目指す中期経営計画の戦略推進が、予知保全システム導入の主な目的だ」と述べている。

従来の事後保全や予防保全には、突発故障への対応や非効率な部品交換(オーバーメンテナンス)といった面で限界があった。新サービスのITOKIアドバンスドメンテナンスは、IoT、AI、ビッグデータを活用して最適なタイミングで保全を行い、これらの課題を解決する。主な導入メリットは、ダウンタイム回避による生産性向上、無駄な部品交換の削減、保全業務の効率化と保全人員の人件費削減、AIによる診断知見の継承を通じた後継者問題の回避の五つだ。
イトーキ 電子機器商品部 ソフトウェア設計課 課長の堤 康次氏は、このシステムの開発背景を「物流の止まらない運用を実現するため」と説明する。スマートメンテナンスの対象は、納入実績約750機、40年ほどの歴史を持つシャトル式自動倉庫「システマストリーマー SAS-R」である。故障のAI解析に必要なデータは、水平走行する小型の台車であるドーリー(走行距離、動作回数など)や、垂直昇降機でラックの各段に商品を昇降させる機能を持つリザーバー(昇降動作距離、ベルト異常など)から収集され、最長15年分が長期保存される。

物理的環境差(寒暖差、ノイズなど)やベルトの張力の季節性によるデータの変動を、イトーキの業務知識に基づくデータ加工(平準化)により吸収している。これにより、AIが単純な環境ノイズを異常と誤判定することを防ぎ、高精度な予知保全を実現している。
予知保全のモデル開発効率化と高精度を維持するために、Oracle Autonomous AI DatabaseやOCI Data Scienceに搭載されている「AutoML(自動機械学習)」機能が活用されている。湊氏はAIの活用でOracleを選定した理由を、「AIの食料となるデータのハンドリングのエキスパート」である点と、「SAS-Rが止まると顧客の出荷が止まる」というミッションクリティカルシステムとしての高い信頼性だと説明する。
イトーキ特許の「入庫制限機能」で停止回避
スマートメンテナンスの特長の一つは、イトーキが特許を取得している「入庫制限機能」である。AIが機器に故障の兆候(いつもと違う状態)を検知した場合、システムは自動または手動でその機器への入庫を制限する。これにより、異常機器の使用を避け、システム全体の停止リスクを低減しつつ、すでに入庫済みの荷物は継続して出庫できるため、物流業務への支障を最小限に抑えることが可能となる。
本システムは新規導入だけでなく、既存のSAS-Rへの導入も可能だ。後付けの工事(センサー追加など)とデータ学習期間を経て運用開始となる。
日本オラクル ストラテジック・クライアント統括 ソーシャル・デザイン推進本部 本部長の井上 憲氏によると、AIモデルを各拠点に適用し、高精度な予知保全を実現するためには、物流機器が稼働する現場の多様な環境要因に対応する工夫が決定的に重要だと説明する。物流機器は納入される拠点により物理的な環境差が存在する。具体的には寒暖差や空港付近など特定の環境でのノイズなどが考えられる。多くのデータで汎用的に作成したAIモデルを「単純に各サイト側に展開しても、じつはうまくはまらないケースが生じます」と井上氏。
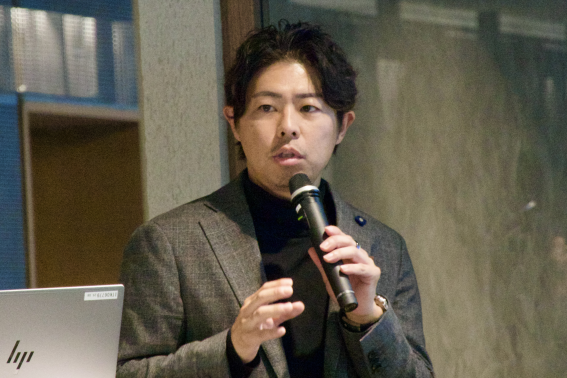
この課題に対処するため、初期開発フェーズにおいて「サイト間の環境差分を吸収するためのパラメータ・チューニング」が実施されている。さらに、ドーリーを動かすベルトの張力はゴム製であるため、夏と冬とで変わるなど季節性が影響を及ぼす。この変化がセンサーデータに大きな差として現れると、AIが単純に異常と判断してしまう可能性があるため、イトーキの持つ業務ナレッジを適用し、データの平準化や加工処理がなされていると説明する。
この業務知識の適用によりAIに対して「これは単純な季節性の差分なので気にししなくていい」と教え込むことができ、AI開発コストを抑えつつ高精度を維持する。このモデル開発と継続的な更新(AIOps)を効率的に行うために、Oracle Autonomous AI DatabaseやOCI Data Scienceに搭載されているAutoML機能が活用されており、最適なアルゴリズムの自動選択や特徴量選択、チューニングがデータベース上で自動的に行われていると、井上氏は説明する。
将来的にはハイブリッド構成と他分野展開を目指す
今後の展望として、両社はサービス運用の拡大に伴い、AIモデルをクラウド集約型で知見を蓄積し、各サイトのエッジPCに展開するハイブリッド構成を促進していくことを検討している。これにより、セキュリティやデータ保全の観点から各サイト内でAIを完結させる。
また、異常発見後のオペレーション効率化も計画されており、過去の保全情報をAIに学習させ、Oracle APEXの活用による情報の可視化や生成AIとの連携も検討されている。イトーキは今後、この予知保全システムを他の物流設備や、研究施設などの「止められない設備」を持つ潜在ユーザーへの展開も視野に入れている。
日本オラクル 専務執行役員 クラウド事業統括の竹爪慎司氏は、「Oracleの目標は、AIを活用することで、業界のエコシステム全体を自動化し、社会や産業が抱える課題を解決することだ。今回の協業は我々の『AIとデータ中心』の戦略とも合致しており、日本オラクルとしてもこれにさらに注力していく」と述べている。
