NECが約11万人の電話基盤を「Zoom Phone」へ刷新 コスト7割削減とDXを加速
日本電気(NEC)は、グループ全社のコミュニケーション基盤刷新と電話関連コストの大幅削減を目的に「Zoom Phone」を採用した。2025年9月18日、Zoom Phoneを提供するZVC JAPANが明らかにした。
オンプレミスPBXの課題とDX推進
創業125年の歴史を持つNECは、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、その一環としてコミュニケーション改革を進めていた。以前から「Zoom Meetings」を活用したロケーションフリーな環境を整備していたものの、オンプレミスPBXの保守期限が迫り、新たな電話システムへの移行が喫緊の課題となっていた。
特に、コロナ禍で浮き彫りになったのは、固定電話のためだけに出社しなければならないといった、場所にとらわれる働き方の非効率さだった。また、誰がどれだけ電話を利用しているか把握できないなど、従来の電話システムでは利用状況の可視化も困難だった。
こうした課題に加え、NECは「クライアントゼロ」として、最先端技術を自社で実証し、その知見を顧客に還元することを重視している。将来的のリアルタイムなコミュニケーションデータの活用を見据え、単なる電話の代替ではない、抜本的なコミュニケーションスタイルの変革を目指した。
NEC EVP兼CIOの小玉 浩氏は、「これは単なる電話の代替ではなく、クラウド化することでさまざまなものがつながり、リアルコミュニケーションデータが価値として使えるようにしていくことでコミュニケーションスタイルを変えていく」と述べ、単なる電話システムの置き換えにとどまらない変革を目指したとしている。

採用の決め手は音質、操作性、そしてコスト
2023年からリプレイスの検討を開始し、複数のサービスを比較した結果、以下の理由からZoom Phoneの採用を決めた。一つ目は音質の良さだ。安定したネットワーク環境下では各サービスに大きな差はなかったものの、自宅などネットワーク環境が不安定な状況下では、Zoom Phoneの音質が際立っていた。重要な会話が電話で行われる傾向があるため、音質にこだわった選択を行った。
二つ目は操作性だ。直感的に操作できるUIで、電話の転送が迅速に行え、誤って切断するなどのトラブルがなかった点を評価した。特に日本ではチーム単位で電話を受けるケースが多く、Zoom Phoneはスムーズな転送操作ができるUIがあったとコメントしている。
最後の理由は、コスト最適化と将来的なデータ活用への期待だ。NEC社内への導入では、オンプレミスPBXと比較して初期費用と運用コストの両方を削減している。さらに、将来的に蓄積した通話データと生成AIを組み合わせたデータ活用を進める際に、データ保管や分析に追加費用がかからない点が採用の大きな決め手となった。
Zoom Phoneは通話の音声データを容量無制限で保存でき、AI機能「Zoom AI Companion」も標準搭載している。NEC デジタルID・働き方DX統括部 シニア主幹の小口和弘氏は、「通話のデータにAIを適用して活用したい際に、追加コストがかからないメリットは大きい」と指摘し、これもりZoom Phoneを選ぶ決め手となったと語った。
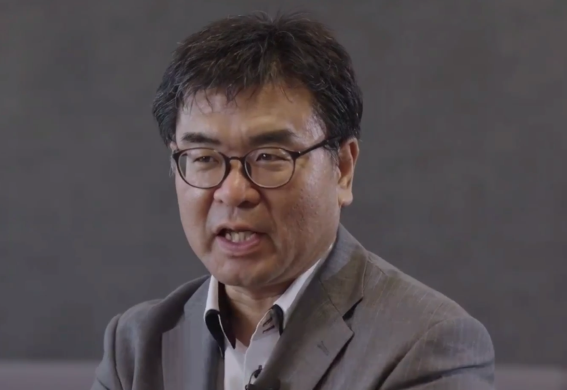
Zoom Phoneの導入にあたりNECは、全国の拠点に点在していたPBX環境の利用実態を調査し、部門ごとに担当者を配置して詳細なニーズを確認している。これにより、グループ全社の国内従業員約11万人を対象とした大規模な移行を、約10カ月という短期間で完遂した。Zoomの技術サポートも移行プロセスを支えたという。
導入効果と今後の展望 「AIネイティブな働き方」の実現へ
Zoom Phoneの導入後、NECは電話関連コストを従来比で約7割削減することに成功した。オンプレミスPBXの撤廃と通信回線の最適化により社内設備を大幅にスリム化した。具体的には、外線が7割、内線が9割減り、PBXがゼロになった。
また、従来は固定電話でしか受けられなかった電話にも、スマートフォンから応対できるようになり、よりロケーションフリーな働き方が推進可能となった。管理部門では通話の利用状況をリアルタイムで把握できるようになったことで、誰がどれだけ電話を使っているかを把握できないような従来の課題解消に大きく貢献している。
NECのコミュニケーション改革は、現在「データドリブン×生成AI」という次の段階へと進んでいる。Zoomプラットフォームから得られるリアルコミュニケーションデータを軸に、メール履歴やプロジェクトファイルなどの社内の既存ストックデータや、自社開発の生成AI「cotomi」と組み合わせてナレッジを再構築し、AIを活用した日々の業務効率化を推進していく計画である。
小口氏は、「音声は極めて重要なものだと思っており、テキストのドキュメントでは把握できない感情面やカジュアルな会話の中にしか残らない情報が得られる」と指摘し、音声データにさまざまなプロジェクトの情報を組み合わせ、それにAI技術を適用して日々の仕事をより楽にしたいという。
NECではWeb会議でも「Zoom AI Companion」が活用されており、会議の記録や要約、アクションアイテムの精度が向上し、本来集中すべき業務に集中できる環境の実現を目指している。小玉氏は「NECは変化を捉え、AIを賢く使い、AI同士が会話する世界を創造することで、1年後、2年後には全く異なる世界に持っていける」と考えており、「AIネイティブな働き方」を支える重要な柱としてZoomとのパートナーシップを位置づけている。自社でのZoomの活用というクライアントゼロの実践を通じて得られたナレッジは、顧客や社会へも還元していく。